TITLE:【Others】2005年出版『あのひとが来て』
『あのひとが来て』
絵:山本容子
曲:谷川賢作
詩:谷川俊太郎
株式会社マガジンハウス 2005年9月30日刊行
2005年、谷川俊太郎さんの詩と谷川賢作さんの音楽、そして山本容子の絵で、一冊の本が誕生しました。CD付で。
書籍は絶版となっていますので、版画作品をSHOPにアップいたしました。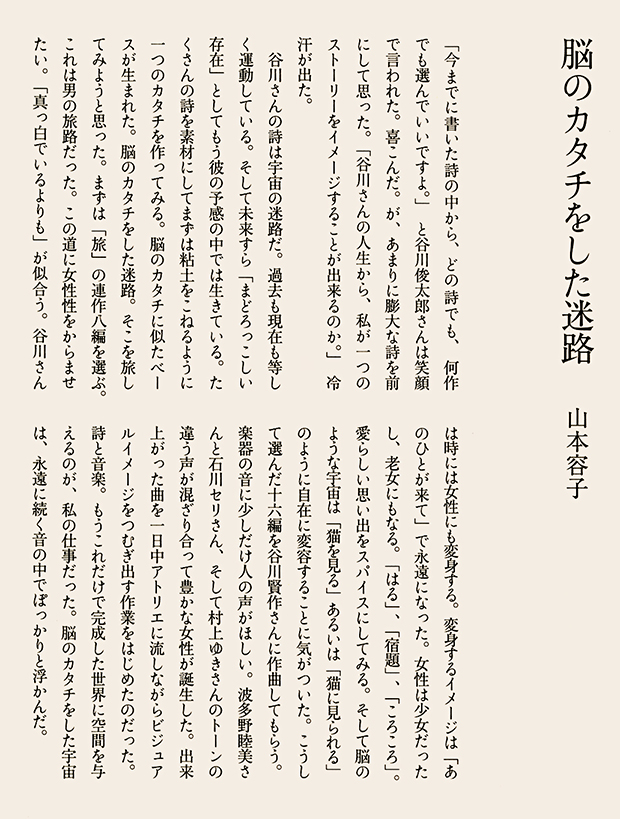
『あのひとが来て』より、あとがき
400.jpg)
『あのひとが来て』
絵:山本容子
曲:谷川賢作
詩:谷川俊太郎
株式会社マガジンハウス 2005年9月30日刊行
2005年、谷川俊太郎さんの詩と谷川賢作さんの音楽、そして山本容子の絵で、一冊の本が誕生しました。CD付で。
書籍は絶版となっていますので、版画作品をSHOPにアップいたしました。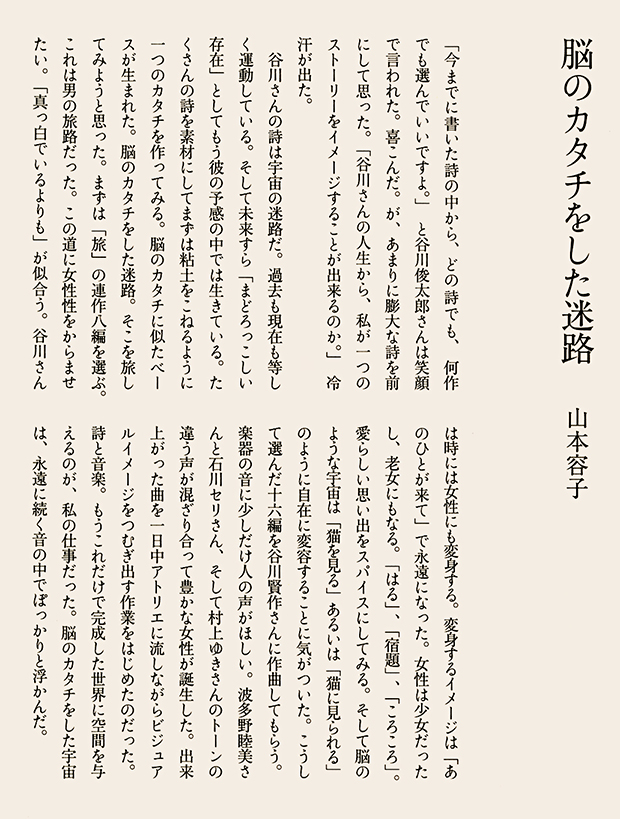
『あのひとが来て』より、あとがき
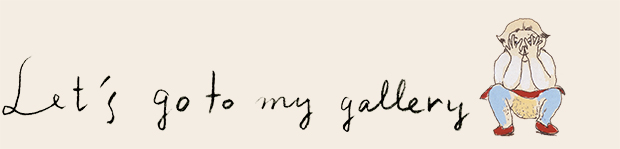

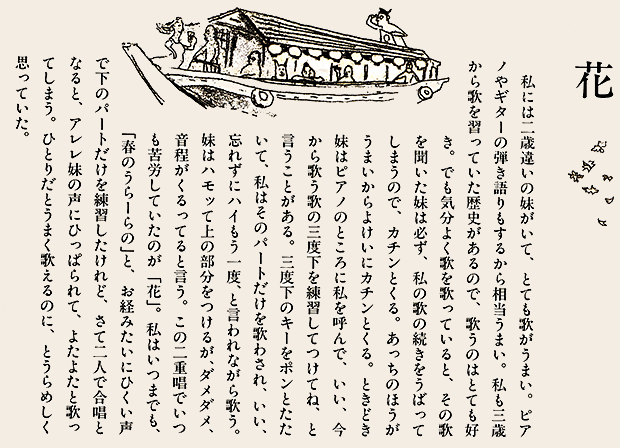
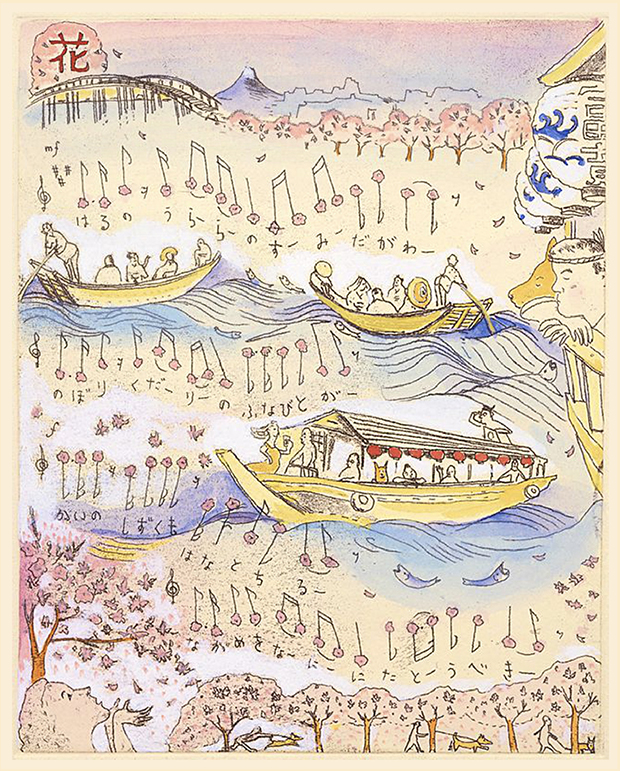
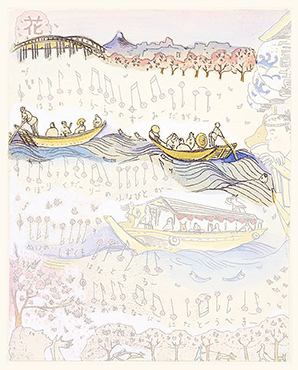
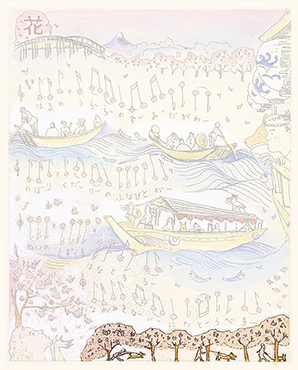

2012年4月から読売新聞夕刊の隔週火曜日に、現代の人間関係のありようや世相を考えるエッセーを集めた「たしなみ」のコーナーの挿画を制作しています。
2020年9月からの作者は星野博美さん(作家・写真家)、恩田侑布子さん(俳人)のお二人です。9年目に入った連載を引き続きお楽しみください。

©Yoko Yamamoto
読売新聞夕刊「たしなみ」挿画、2021年3月31日のテーマは「お墓参りのマナー」星野博美さんです。
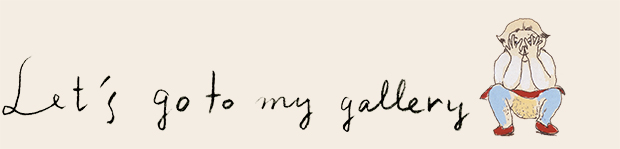
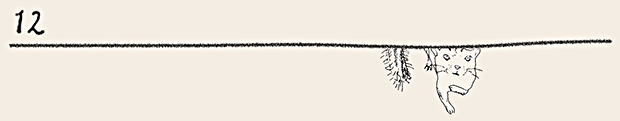

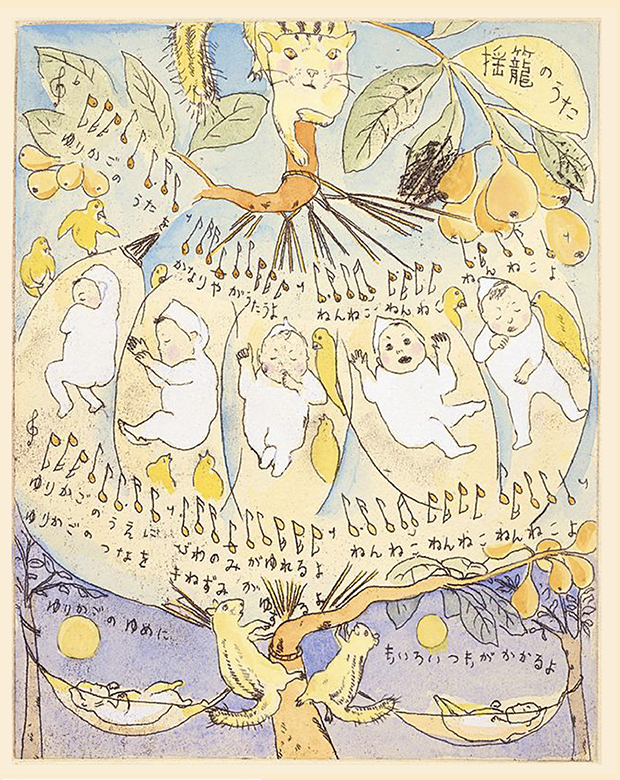
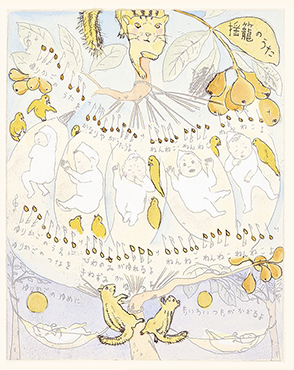
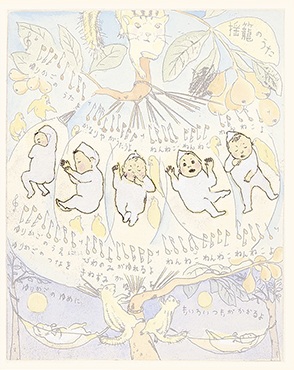
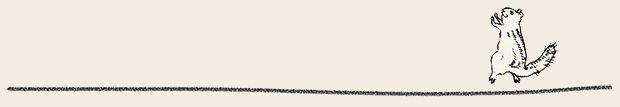
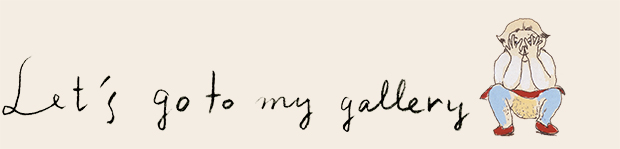
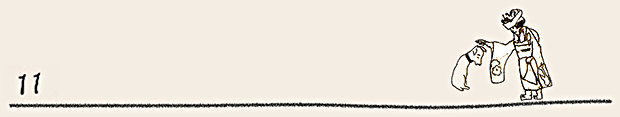
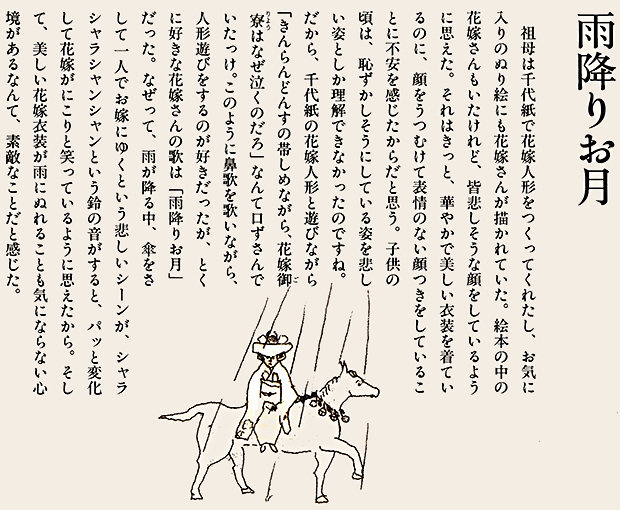
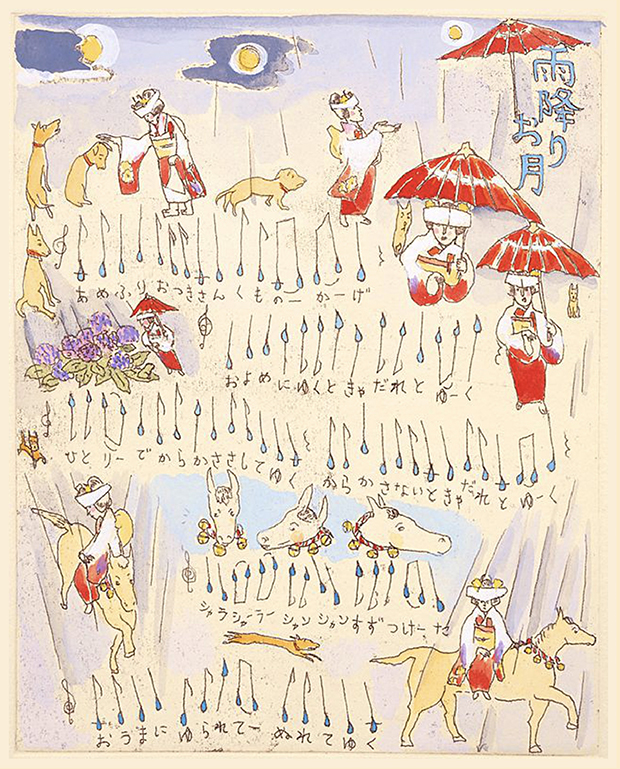
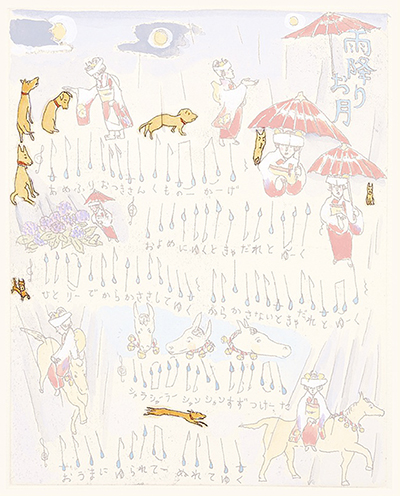
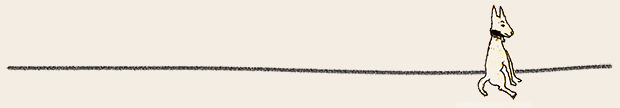
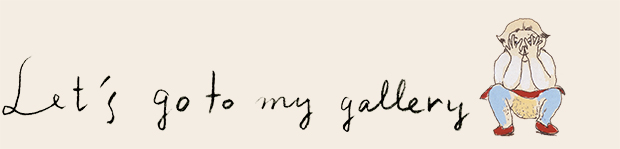
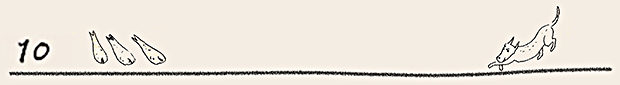
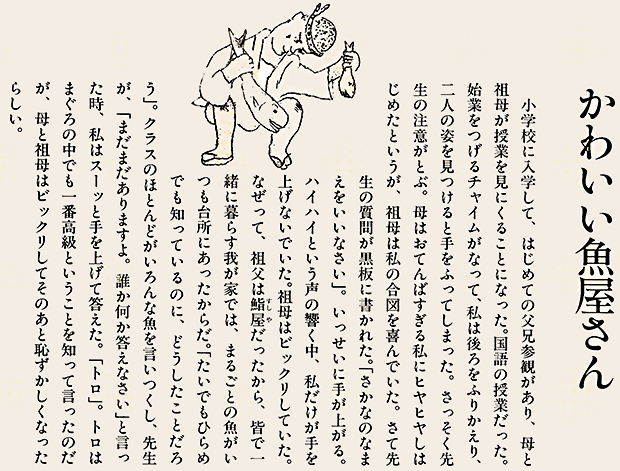
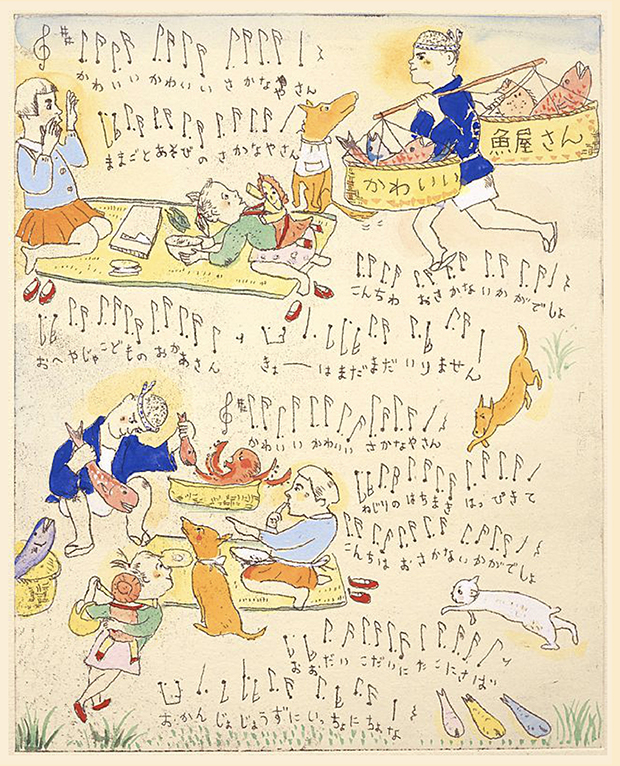



2012年4月から読売新聞夕刊の隔週火曜日に、現代の人間関係のありようや世相を考えるエッセーを集めた「たしなみ」のコーナーの挿画を制作しています。
2020年9月からの作者は星野博美さん(作家・写真家)、恩田侑布子さん(俳人)のお二人です。9年目に入った連載を引き続きお楽しみください。

©Yoko Yamamoto
読売新聞夕刊「たしなみ」挿画、2021年3月10日のテーマは「美に触れ、祈るマナー」恩田侑布子さんです。
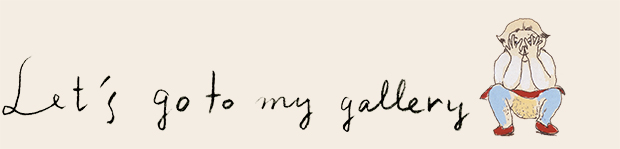
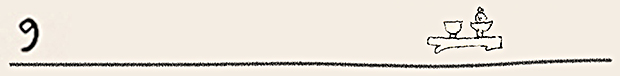
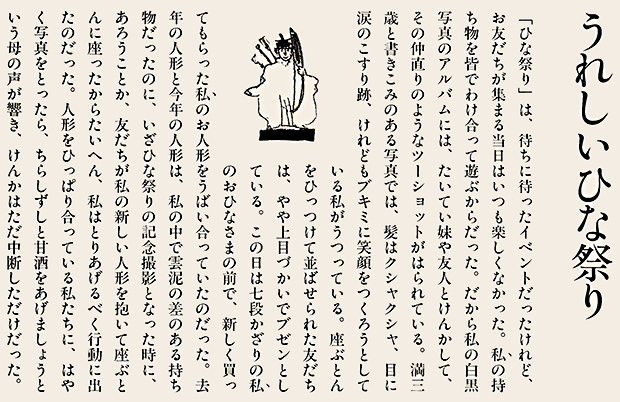
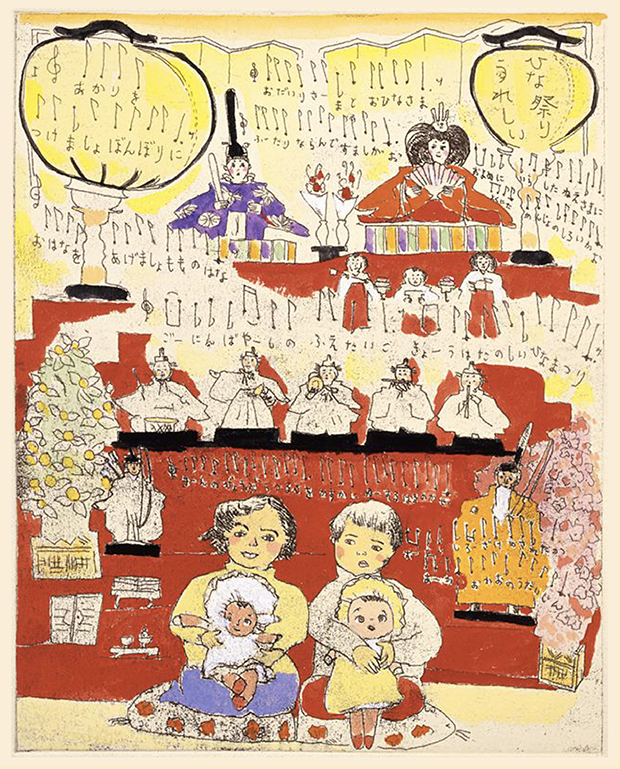
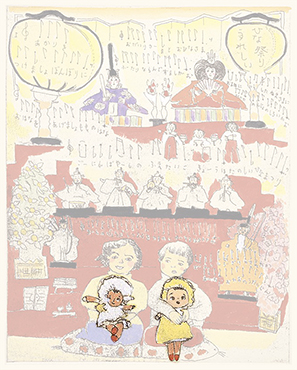
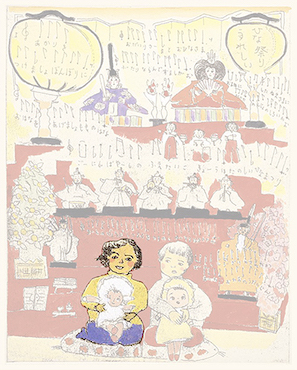

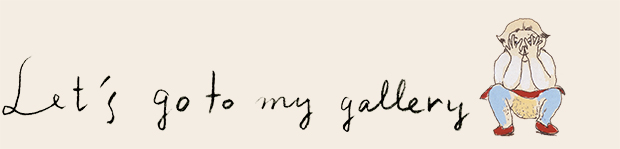
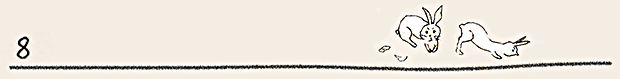

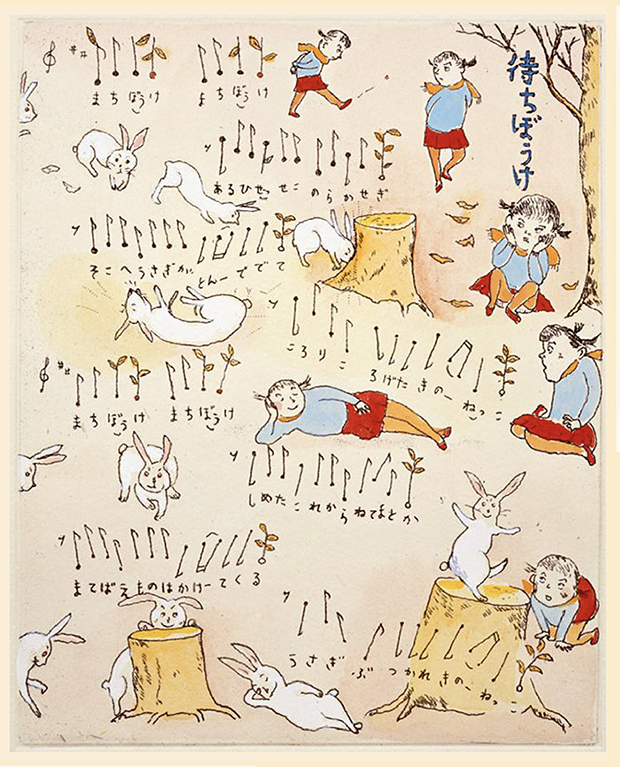
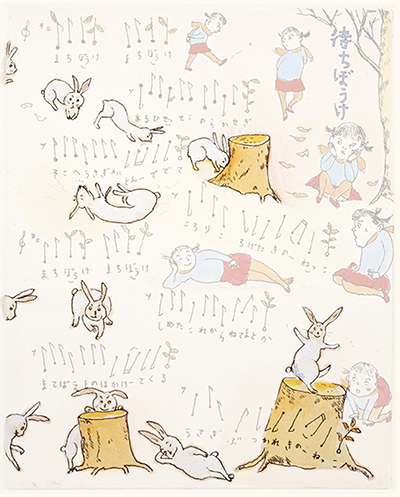
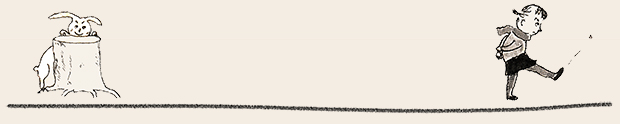
2012年4月から読売新聞夕刊の隔週火曜日に、現代の人間関係のありようや世相を考えるエッセーを集めた「たしなみ」のコーナーの挿画を制作しています。
2020年9月からの作者は星野博美さん(作家・写真家)、恩田侑布子さん(俳人)のお二人です。9年目に入った連載を引き続きお楽しみください。
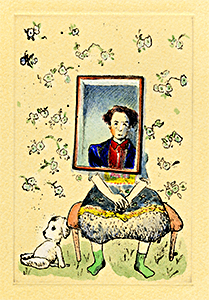
©Yoko Yamamoto
読売新聞夕刊「たしなみ」挿画、2021年2月24日のテーマは「オンライン会議のマナー」星野博美さんです。